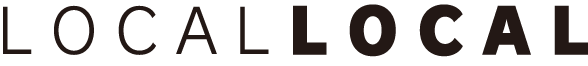

地域と人、農業の在り方や生き方など、そこにすべてを包んだような「しまんと流域農業」です。哲学的でもあります。
5年ぐらい前にふと、自分が長い間手がけてきた「お茶」や「栗」「ヒノキ」「芋」などの商品を振り返って眺めてみたことがあった。自分がドローンになったみたいに空中から四万十川を地理的な1本の線として俯瞰して見ているような感覚があった。そのとき、この流域の人々の農業という営みが1つのブランディングではないのかと気づいた瞬間、ひらめいたのが「しまんと流域農業」というネーミング。その考え方をネーミングとしてブランディングをした後、どう展開していけばよいのか。どんな農業だったらよいのかと思うわけ。そこで「しまんと流域農業」というコトバの下に「Organic」という言葉をセットした。哲学とまでは言わないけれど、このコトバですべて通じるんとちゃうか?

まず、考え方をコトバでデザインする。梅原さんのデザインスタイルの特長でもありますね。
コトバの伝わるボリュームというのはボクがある意味、得意とするところでもあって、このコトバを聞くと、その状況がいっぺんに伝わることを自分の職業にしている。その一部に絵を描いたり、デザインしたりすることがあるのだけど、やりたいことは大きなコミュニケーションを相手に楽しく受け渡すことであり、それを「デザイン」というのではないか。ボクはデザインというものをそう解釈しています。

もう30年以上、デザインを通して廃れようとしている四万十の一次産業を掘り起こし、産品として育ててきました。しまんと流域農業という考え方は集大成のようにも思われます。

自分たちがやってきたことはすべて「自然が資本」だった。それは30年経って見えてきたこと。かつて四万十川のほとりに4年ほど住んでみたけれど、当時、そこに地域の「生き方」はなかった。感じたのは農業がちっとも楽しそうに見えんなあということ。
たとえば茶葉を摘んだら軽トラで1㎞離れた対岸の茶工場に軽トラで茶葉を持っていけば、計量して換金できる。摘んだらネットにいれてポーン。はい、なんぼ。このスタイルよ。どこで誰に飲まれるかも関係ない。農業は生産者が見えるから愉しかったりもするのだけれど、そこが届いておらず、いわゆる従来の慣行農業をこの四万十川のほとりの狭い土地でもやっているわけです。それはボクが現在暮らしている平野部と同じ手法の農業。効率がいいから、化学肥料・農薬を使ってシシトウ、オクラを作ればお金になるかもしれないけれど、土地の条件はまったく違うやん。四万十の農業のやり方に対して「そうじゃないでしょ」と、ずっと疑問を持っていた。川に沿って狭隘な段々畑があるこの地形や風景、それを欠点と捉えるか、個性と捉えるか。ボクは欠点と思われるものはすべて個性だと思っています。それが自分の「土地の力を引き出すデザイン」でもあります。

今、お茶の話が出ましたけれど、私、梅原さんが地域の神祭の席で「お前ら、ええ加減にせえよ。俺、ここに来て初めて知ったわ。えっ、茶畑あったん?みたいな。茶というものに愛情がない。あんたら、四万十を1つも守ってない」と、茶工場の工場長に怒ったハナシが大好きです。 (笑)
1983年だったかな、NHKのドキュメンタリー番組で「最後の清流」と紹介され、四万十川が一気に全国に知られるようになった。なのに、四万十で生きることのうっすらとした誇りみたいなもんが、あんたらの中にあるわけではなかったんかい ?と。NHKが作った、でっち上げやんかと、ふつふつ怒りが湧いてきたのよ。そのお茶が「しまんと緑茶」になったのは、ぼくが四万十に4年住み、高知市に帰ってきて3年経ったころ。地域がそれに気づくまで7年かかった。今は「それ、違うんじゃない?」と言う人が、誰もいない世の中になっている。だから、「そうじゃないでしょ」と言うのが、ぼくの仕事。でも「そうじゃないでしょ」を具体的にデザインで可視化するわけだから成立しているんじゃないかな(笑)。ただ文句を言っているオヤジではアカン。解決策を持っておこらんと面白くない。
つまり、この狭わいな四万十の山畑の風景がベースにあってこその「しまんと流域農業」であると。


川筋を走っていると、いつもブルドーブルドーザーやショベルカーの音が聞こえる。河川敷にある狭い畑を圃場整備して広げる工事をやっているわけよ。おそらく農水省の事業だと思うが、ぼくはここに違和感がある。ここは狭隘な土地で効率が悪いから良くするために1㌶を3㌶にしてあげるというのはとても頭のカタイ発想で、中山間地域の現実に合っているとは思えんのよ。その土地土地に適した作物があるはずやん。オーストラリアは広い土地でカボチャやトウモロコシを作っている。日本にもそういう野菜がどんどん輸入されている。よそから購入する方が安い。向こうは土地も広いから効率も良い。では四万十は効率が悪いから良くするために1㌶を3㌶にしてあげるというのが、とても官僚的な発想。それは中山間地域の現実に合っているとは僕には思えんのよ。

戦後、生産性や経済性ばかりを追いかけてきた日本の在り方に、梅原さんはずっと違和感があると言い続けています。
日本の戦後の生産性をあげないといけないとやってきて、エレクトロニクスも車も農業もそういう生産性が中心になってやってきた。さっきのカボチャも生産性でいえばオーストラリアには敵わんやん。そっちじゃないじゃない。生産性ではない価値観、安全性に目を向けて、野菜の価値を上げていけばいいのに、そうはならんの。誰もそんな価値観を持っていない。農薬かけて化学肥料を使って、圃場も広くして生産性をあげんとアカン。これが官僚的だと思うわけ。いわゆる賢い人のデスクワークの頭の中の生産性を上げる概念であって、安全なものを作って別のステージで売るという考え方はなかった。政策を考える人は「生活者」ではないかね。
たとえば絶滅しようとしていた栗を「しまんと地栗」として商品にした。山へ行って荒れ果てた栗園を見て、これでええやん、オーガニックやん!と考え、実際に商品にし、工場もでき、通販や店舗で5億円ほど売れるようになってきた。その価値観を作ったので、リアルな証明はそれで一つしてある。「しまんと地栗」は土地に適ったもののブランディング。いや、土地のブランディング、流域のブランディングとちゃうの?うちの土地にはこの作物が適切であり、オーガニックという方法で安全なものを作っています。それが清流と生きる流域の考え方である。「考え方」がブランドである。四万十川に習いその安全性を付加価値とするべきではないか。
「しまんと流域農業」は生産性を上げるためのコンテンツではない。自分たちの狭わいな土地でしか農業ができない。そういう特別な土地の個性、そこから発する安全なもの、少量の土地だから少量の安全なものを作ってそこに価値を見出していこう。それが「しまんと流域農業」のベースにあります。そういう価値を見出すチカラがローカルのチカラです。

梅原さんのいう「ローカルが持つべき価値を見出すチカラ」ってなんですか?

ボクがここで大きく言いたいし、問いたいし、伝えたいのは、人が生きていくのに何が大事なのかということ。「風土から読み取るチカラ」がローカルのチカラじゃないのか。そこにローカルの意味があるんじゃないの? ボクたちはローカルに住んで何が大事なんや、この川が流れているということはどういうことなんやと、この風土から読み取る感受性みたいなものがチカラになって、何かを起こさないといけない。そのために「足もとを見よう」と言い続けてきたわけです。何が大事なのか読み取るチカラがないのが政府であって、いわゆる生産性を上げるために化学肥料や殺虫剤を使って、それで生産性をあげていくこと自体が、生活者ではない、お勉強ばかりした人、のデスクワークやん。


その霞ヶ関嫌いであったはずの梅原さんがここ3年、農水省と一緒にこの「しまんと流域農業」をプロジェクトとして進めています。中央への反骨精神というのは水に流したんですか? (笑)

3年前、農水省が「みどりの食糧システム戦略」という政策を打ち出した。2050年までに日本の農地の1/4をオーガニック化する、有機化するというプランです。農薬を2030年までに30%減らすというようなことが、この政策の中心ですわ。農水省が急にそんなことを言い始めたわけです。オーガニックで行くという考え方は、ぼくらの方が先だった。けれど農水省の考え方とぴったり合っている。ほんなら農水省と一緒にやっていこう。補助金もある。同じ方向に行くにあたって、しまんと流域農業と「緑の食料システム戦略」という言葉がリンクしてきた。政府がオーガニック化にチカラを入れていくのに野党が反対をする。なんでや、俺は賛成やで。農水省の力を借りながら、このしまんと流域農業を進めていますーというコトバを本気で使うようにしている。良いことはええやんというのが、自分の考え方の中心。

今まで農水省はコンセプトがなさすぎたけれど、ようやく追いついてきた感じですか?

日本の食料自給率はカロリーベースで38% (2022年度)。先進国の中では最も低い。これは何十年経っても上がらんのよ。農水省があげようとしても上がらない。2030年の目標値45%には遠い状況よねえ。
アメリカやヨーロッパでは「グリーン政策」をやっていて、アメリカではオーガニックに、ヨーロッパではビオの作物にシフトしている。フランスでは化学肥料で土地が荒れてくるのをずいぶん前から察知して、国会で決め、有機栽培の農家には結構な補助金を与えることで農業の方向性がぐっと変わった。フランスのスーパーに行けばBIO、BIO、BIO。ビオのマークの野菜や加工品がたくさんある。フランスは特に小規模でオーガニックでやってくれるところに奨励金を出して、農業の振興をオーガニック化しています。ヨーロッパではもう2割ぐらいがオーガニックなのではないかな。
これに大きく一歩遅れているのが日本です。グリーンの食料戦略をコトバで立てた。しかしまだ中身は何にもない。そこにあったのが私達の「しまんと流域農業Organic」。農水省職員と一緒になって大きなシンポジウムを毎年開催するなど、関係性を耕しながらオーガニック化に向かってタネを蒔いてきました。これからどんな可能性の芽が出てくるかなというところ。


梅原さんにとって、オーガニックとはなんですか?
ぼくは毎年2回ぐらい、パリに行くのが恒例なんやけど、滞在期間中は必ず、日曜日にやっている「ラスパイユのビオの市」に行きます。「オーガニック」のことをヨーロッパでは「BIO」といいます。そこでチキンをやワイン、塩やパン、野菜を買ってホテルでランチを食べる楽しさ。ビオの食材は味も違うし、売っている人の顔も違う。別の曜日にも「市」をやっていたのでそこを通ったら、ニオイがまったく違うことに気がついた。「豊かではないニオイ」。そこで「ケミカル」と「オーガニック」の違いを「パリの市」で知らされた。売っている人の顔が違う。慣行農業とビオの人たちとは思想の違い、考えの違いを含め、それが食べ物の「味」「におい」に現れていることを「市」で体感した。しまんと流域農業オーガニックの根っこは、そういう自分の体感にある。自分も野菜を作っていて、農薬や化学肥料は使いたくない。それが普通の生理的感覚とちゃうんかな。根本的な人間的な部分、もともとあるハートの部分でええんちゃうの。体感で知るということ。そのことをボクは「体内マーケティング」と言っている。自分のカラダや皮膚感、自分の感性や感覚をスキャニングし、マーケティングをしてデザインとしてアウトプットしていく。

今、流域では具体的にどんな農業が進められているのでしょうか?

最初はキュウリやトマト、ほうれん草やクレソンなど、多種な野菜をイメージしていた。しまんと流域農業のトマト、ニンジンというと、とってもみずみずしくておいしそうやんか。でもオーガニックで作っている流域の農家の人たちに話を聞くと、みんな、やり方が違うんよ。多種多様なやり方、方法論があって、作り方を一つの基準として固めるためにはある程度、方法論を同じにしないといけないけれど、なかなか難しく、模索しているところです。
そこで今、一番簡単にオーガニックができる方法としてさつま芋を作っています。河川敷に耕作放棄地がたくさんあって、そこを耕して芋のツルを植える。芋はツルのどこを切っても根が出てくるんよ。植えて5ヶ月足らずで光合成できて、根っこにデンプンができる。それが芋なわけ。さつまいもは荒れ地ほどよろしい。河川敷は水はけもよくて、芋づくりには適してもいます。肥料も要らんし、連作にも相当強い作物でもある。栽培するのにそんなに手もかからんので、農家さんにとっても作りやすいし、ほかの仕事をしながら芋農家にもなれるんちゃうかな?収穫した芋は、四万十ドラマが買い上げて加工し、商品を作るーということをやり始めた。

四万十流域は、昔、芋づくりが盛んに行われていたそうですね。すでに四万十ドラマから「ひがしやま」という焼き菓子が販売されていましたが、2023年には干し芋も発売されています。

芋は四万十のこの地に合った作物であり、地域の小さなビジネスに育っていく。こうして「しまんと流域農業」へとつながっていくわけ。そこにデザインが要る。土地の力を引き出すデザインよ。
干し芋は白芋と人参芋の2種類で、四万十では昔から人参芋が作られていますが、全国的では希少な品種らしい。今「MUJI」と話をし「人参芋」で作る新商品を開発し始めた。MUJIと四万十町は協定も結んでいますし、一緒にできることがまだまだあるんとちゃうかな。今はまだまだ「しまんと流域農業」については整理をしている段階で、プロセスをデザインをしていかないといけない。
MUJIは「しまんと分校」という田舎と都会が交流し、ともに学び合うコミュニケーションの場づくりにも共感をしていただいている。しまんと流域農業を、これからさらにどうデザインしていくか。これが自分の最後の大きな仕事であるという気持ちでいます。

